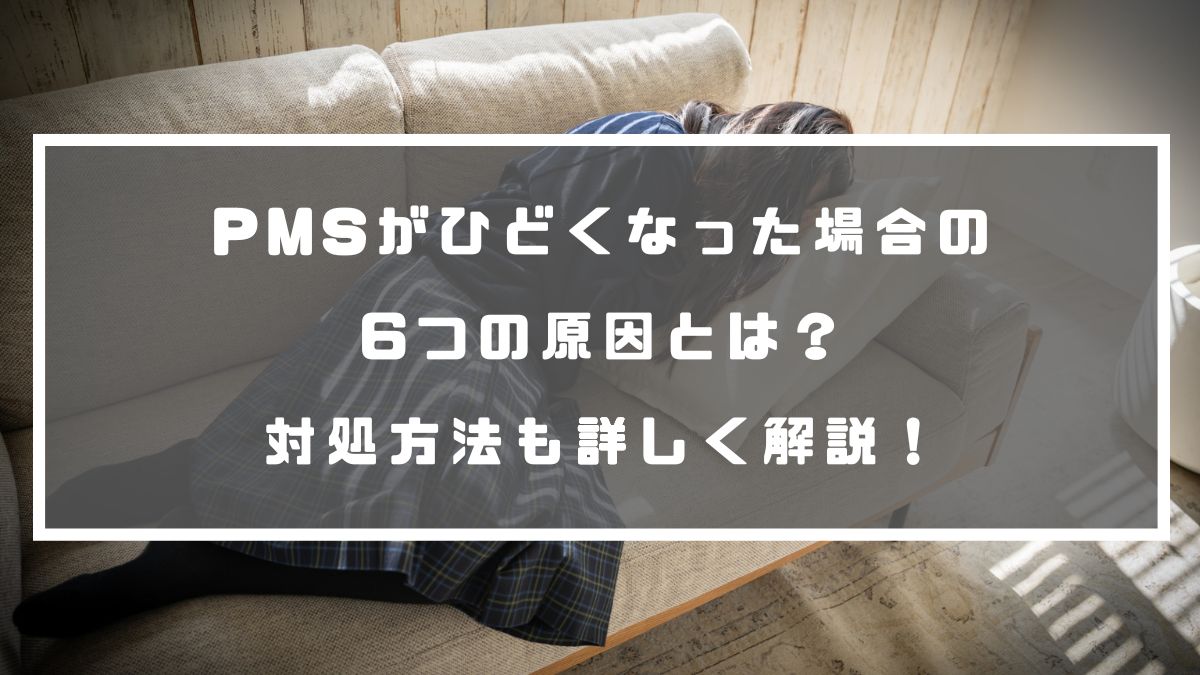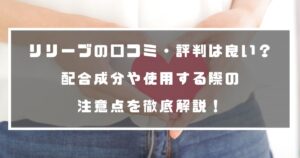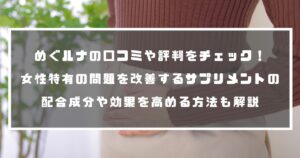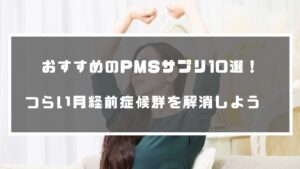「月経前になると身体の調子が悪い」、「精神的に不安定になる」という方はPMSの可能性があります。
PMSにはいくつかの原因が考えられ、薬の服用や生活習慣の改善によって症状を緩和できます。
本記事では、PMSの症状や原因、対処方法を紹介します。
毎月のように月経前の不調に悩んでいる方や日常生活に影響が出てしまっている方は、ぜひ参考にしてみてください。
PMSとは

月経前に起こる身体的症状や精神的症状の総称がPMS(Premenstrual Syndrome)です。
日本名では月経前症候群と呼ばれており、日本人女性の半数以上がPMS症状を抱えています。
しかし、自身がPMSであることを自覚していない方やPMSの対処方法を知らない方が多く、知らないうちに生活の質が下がってしまっている実状があります。
まずは、自身の症状がPMSに当てはまるかチェックしてみましょう。
症状
PMSでは、月経周期によるホルモンバランスの変化により身体的症状や精神的症状が現れます。
月経の10~14日前から症状が現れ、月経が始まると徐々に症状が治まる傾向にあります。
PMSでよく見られる代表的な症状を、身体的症状と精神的症状に分けて紹介します。
身体的症状
- 乳房の張りや痛み
- 下腹部の痛み
- 腰痛
- 便秘、下痢
- 頭痛
- むくみ
- 肌荒れ
- 不眠、過眠
- 食欲増進
これらの症状は、月経前の女性の大半が経験したことがあるでしょう。身体に現れるさまざまな症状は、月経周期によって変化するホルモンバランスが影響しています。
精神的症状
- 気分の落ち込み
- イライラする
- 感情の浮き沈みが激しい
- 不安感
- 些細なことで涙が出る
- 集中力の低下
- 意欲の低下
月経前にイライラしたり感情的になりやすかったりする感情の起伏もPMSの症状のひとつです。
うつ病のような精神的症状が強く現れる場合は、PMDD(月経前不快気分障害)の可能性もあります。
原因
PMSは現代病であり、ストレスが溜まりやすい環境や食生活、生活習慣の乱れが原因のひとつです。
しかし、外的要因のみならず身体の中で起きているホルモンバランスの変化も大きく関係しています。
PMSを引き起こす原因を詳しく解説します。
女性ホルモンの急激な変動
10代頃に初潮を迎え、閉経する40~50代までの約30~40年間、毎月のように月経が訪れます。
月経がある女性の体内では、月経周期によってホルモンバランスが変化し、排卵や月経を誘発しています。
月経が始まる約2週間前に排卵があると黄体期になり、黄体ホルモンであるプロゲステロンの分泌量が増加します。
プロゲステロンは妊娠や出産に必要不可欠なホルモンですが、プロゲステロンの急激な変動がPMSを引き起こす原因のひとつです。
偏った食生活
現代人に好まれるジャンクフードや手軽に食べられるファストフードなど、偏った食生活は生活習慣病のみならずPMSの原因にもなります。
欧米の食文化であるジャンクフードは、カロリーや塩分が高く、脂っこい反面栄養価が低い食事です。
また、朝食を抜くことやダイエットによる無理な食事制限も身体に悪影響を与えます。
発症時期
PMSは、10代後半から40代前半までの性成熟期の女性が発症します。
妊娠や出産経験がある女性は精神的症状が強く現れることが多く、妊娠出産、仕事や私生活のストレスが溜まりやすい30代がPMS発症のピークです。
しかし、妊娠や出産経験の有無、年代にかかわらず症状には個人差があります。
10代からPMSに悩んでいる方がいる一方、閉経まで目立った症状を感じない方もいます。
PMDDとの違い
PMSとよく似た病気にPMDD(月経前不快気分障害)があります。不快気分障害の名のとおり、月経前になると精神的症状が強く現れる精神障害の一種です。
月経の約2週間前から症状が現れ始め、月経が始まると徐々に軽減します。
- 理由もないのに悲しくなる
- 些細なことで涙が出る
- 不安感や緊張感が強い
- 怒りの衝動を抑えられない
- 感情の浮き沈みが激しい
- 意欲や集中力の低下
- 人間関係がうまくいかない
- 不眠、過眠
- 希死念慮(死にたくなる)
PMSは主に婦人科を受診します。一方、PMDDはうつ病や双極性障害との判別が難しく、併発している可能性もあるため、精神科や心療内科の受診が推奨されます。
また、PMSとは治療方法が異なるため、精神的症状によって日常生活に支障がある方は、自己判断せず医師に相談してください。
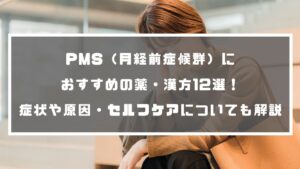
PMSがひどくなった場合の6つの原因

PMSはさまざまな生活習慣によって、症状がひどくなる場合があります。
症状悪化に繋がる原因を6つ紹介します。
ホルモン量減少
女性ホルモンには、卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)という2種類のホルモンが存在します。
月経周期による黄体ホルモンの増減がPMSに関係していますが、女性ホルモンが減少するとPMS症状が強くなる傾向があります。ホルモンを分泌するためには脳からの指令が必要です。
しかし、ストレスや生活習慣の乱れによって正常な指令が出せなくなるとホルモン量が減少し、PMSをはじめとする身体の不調を引き起こします。
30代後半から40代の更年期が近い女性は、とくに女性ホルモンが減少しやすいとされています。
カフェイン摂取
前述のとおり、黄体ホルモン(プロゲステロン)が減少するとPMSの症状が強くなります。
コーヒーや紅茶、緑茶などに含まれるカフェインは、プロゲステロンの働きを妨げるコルチゾールというホルモンの分泌を促してしまいます。
そのため、カフェインを摂取しすぎるとPMSの症状を悪化させてしまうのです。
- コーヒー
- 紅茶
- 緑茶
- ウーロン茶
- エナジードリンク
- チョコレート
カフェインゼロの飲料を選び、月経前はなるべくカフェイン摂取を控えることが大切です。
喫煙
喫煙が肌荒れやシミなどの肌トラブルを引き起こすことは有名ですが、PMSの諸症状にも大きく関わっています。また、タバコに含まれるニコチンは卵巣機能に障害を与えます。
卵巣機能が低下すると女性ホルモンの生成や作用が正常におこなわれなくなるため、結果的に喫煙が女性ホルモンの減少に繋がるのです。
飲酒
エストロゲンは、アルコールと同様に肝臓で分解されます。
しかし、過度な飲酒によって体内のアルコール量が増えると、アルコールの分解を優先するためエストロゲンが体内に残ってしまいます。これによりエストロゲンの量が増加します。
一方、プロゲステロンはアルコールによって減少する場合があるため、エストロゲンとプロゲステロンのバランスが乱れてしまいます。
女性ホルモンのバランスが大きく変化するため、日常的に飲酒する習慣がある方は、PMS症状がひどくなりやすいでしょう。
加齢
本来の女性ホルモンは、月経周期に伴ってバランスを保っています。
しかし、女性ホルモンの分泌量は年齢と共に変化しており、分泌量のピークである30代前半以降は徐々に減少していきます。
そのため、分泌量が増加する20代から30代、分泌量が減少する30代後半から40代頃はホルモンの分泌量が変化するため、PMSの症状も変化します。
20代後半から30代前半は、とくに症状がひどくなりやすいとされています。
ただし、加齢や閉経に伴って発症する更年期障害と症状が似ているため、30代後半から40代の女性は更年期障害との関連も併せて判断しましょう。
出産
出産によってPMSの症状がひどくなる原因は解明されていませんが、子育てに伴う環境の変化や生活習慣の乱れ、ストレスの増加が関係していると考えられます。
子育ての悩みや睡眠不足、栄養の偏りなどにより感情の浮き沈みが激しくなり、心身共に疲弊するためPMSの症状が強くなったと感じるのでしょう。
また、出産経験のある女性では精神的症状が強くなる傾向があるため、これまでに感じなかった苛立ちや不安感に襲われる可能性があります。
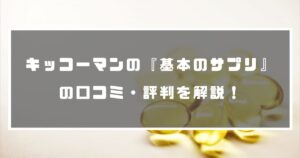
PMSに個人差がある理由

PMSの原因は女性ホルモンの変化や乱れた生活習慣にありますが、自身が置かれている環境や性格によっても症状の現れ方に差が出ます。
- 仕事が忙しく、睡眠不足
- 食生活が偏っている
- 生活習慣が乱れている
- 真面目
- 几帳面
- 周囲からの評価を過度に気にする
- 自身の感情を我慢する
これらに当てはまる方は、PMSを発症する可能性が高いでしょう。症状の程度や頻度には個人差がありますが、乱れた生活習慣を整え、ストレスを溜めないことが大切です。

PMSがひどくなった場合の対処方法
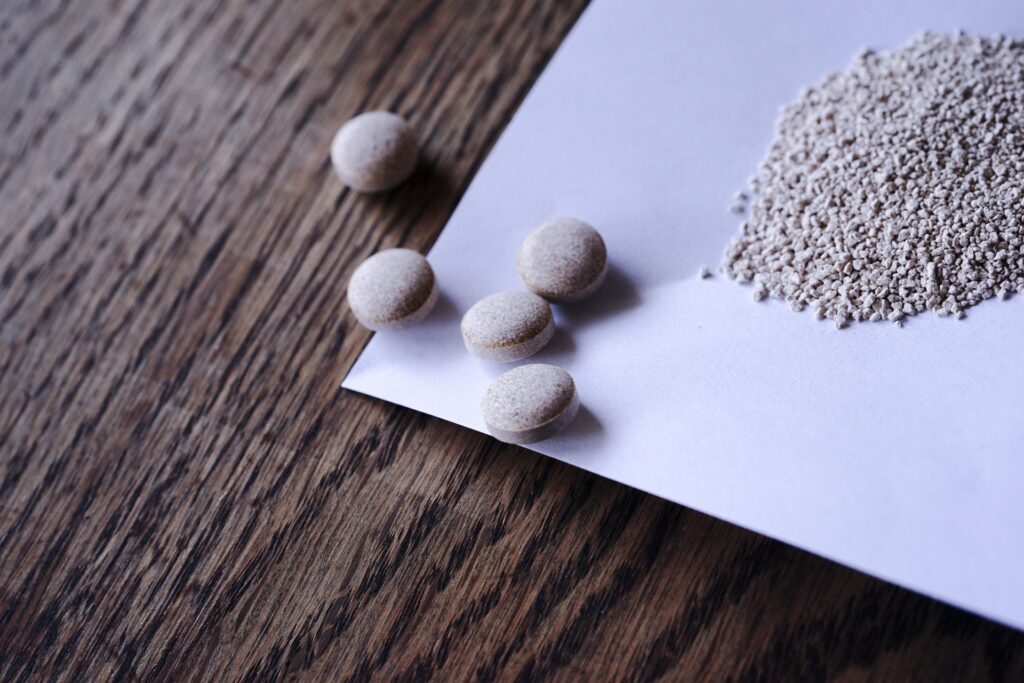
PMSの症状がひどくなってしまった場合には、つぎに紹介する対処方法をおすすめします。
ただし、精神的症状が強い場合や日常生活に支障をきたすほどの身体的症状がある場合はPMS以外の病気の可能性があります。PMSかどうかわからない場合には、まずは婦人科を受診しましょう。
漢方薬
PMSの症状緩和には、漢方薬を処方されることが一般的です。漢方は中国で古くから親しまれてきた医学で、さまざまな生薬を調合して身体の不調を改善させる目的があります。
また、漢方薬によって体質改善や未病の解消も期待できます。PMSに効果的とされる漢方薬にはいくつか種類があり、症状や体質によって選ぶことが大切です。
- イライラしやすい、眠れない:加味逍遙散(カミショウヨウサン)
- 疲労感、身体の冷え、むくみ:当帰芍薬散(トウキシャクヤクサン)
- ストレスが溜まりやすい、頭痛、下半身の冷え:桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン)
- 疲労感、倦怠感、食欲不振:補中益気湯(ホチュウエッキトウ)
漢方薬はドラッグストアなどでも購入可能ですが、PMSの治療目的であれば保険適用で入手できる場合があるため、長期的に服用したい方は婦人科で相談することをおすすめします。
また、漢方薬には顆粒タイプや錠剤タイプがあるため、自身が飲みやすいタイプを選びましょう。
低用量ピル
低用量ピルは、月経にまつわる諸症状の緩和や避妊を目的として処方されます。
ピルには女性ホルモンに似ている成分が配合されており、乱れてしまったホルモンバランスを人為的に補えます。
一般的な低用量ピルは1シートを1周期とし、決められた順番通りに服用してホルモンバランスを調整します。
近年では、低用量ピルをオンライン処方しているクリニックも増えているため、通院が難しい方でも利用可能です。
PMSの他、月経痛や月経周期の乱れに悩んでいる方にもおすすめです。
生活習慣の改善
PMSは生活習慣の影響を大きく受けます。そのため、乱れた生活習慣を改善することで症状が緩和されることがあります。
具体的には、つぎに挙げる点を意識して改善してみましょう。
栄養のバランスを考えた食事を摂る
脂っこい食べ物や偏った食事はPMSを悪化させる原因となります。
イライラを抑えるためにはビタミンB6やカルシウム、不安感や緊張感の緩和にはマグネシウム、腰痛や冷えの改善にはEPAがおすすめです。
- まぐろ
- かつお
- 鮭
- 海苔
- レバー
- 鶏肉
- にんにく
- ピスタチオ など
- 干しえび
- 煮干し
- 昆布
- ごま
- 牛乳 など
- 干しえび
- あおさ
- 海苔
- ごま
- かぼちゃの種 など
- いくら
- すじこ
- さば
- 海苔 など
大豆製品に多く含まれるイソフラボンには、エストロゲンと似た働きがあるとされています。
しかし、月経前の時期にエストロゲンが増えすぎるとホルモンバランスが乱れ、PMSが悪化する恐れがあるため、栄養バランスに見合った量に留めましょう。
適度に運動する
運動をすると、ドーパミンやノルアドレナリンなどのさまざまなホルモンが分泌されます。とくにセロトニンは、ストレス緩和や心のコントロールに効果的なホルモンです。
PMSの改善には有酸素運動がおすすめで、日頃から適度な運動を心掛けることが大切です。
急激な運動は身体や筋肉に負担がかかり継続も難しいため、まずはウォーキングや軽いランニングなど、無理のない範囲で始めましょう。
また、屋外での運動が難しい場合は就寝前の時間を有効活用して、ストレッチやヨガなどがおすすめです。
PMSによるイライラした気持ちや落ち込んだ気持ちを解消するように、深呼吸をしてリラックスしながらおこなってください。
飲酒・喫煙を控える
前述のとおり、飲酒や喫煙はPMSを悪化させる大きな要因のひとつです。
いきなりすべてを絶つことはかえってストレスになるため、まずはアルコールやタバコの本数を減らすことから始めましょう。
本数や頻度を徐々に減らすと同時に、飲酒や喫煙以外の趣味を見つける方法もおすすめです。
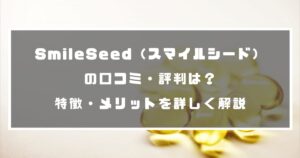
PMSがひどい場合は病気の可能性もある

PMSには身体的症状と精神的症状がありますが、症状が限定されている場合や、限られた症状のみが強く現れる場合には他の病気の可能性があります。
他の病気だった場合は治療方法が異なるため、正しい治療に切り替えなければなりません。
PMSとよく似た症状を持つ病気を3つ紹介します。
うつ病
PMSのうち、精神的症状が強く現れる場合にはPMDD(月経前不快気分障害)を発症している可能性があります。
PMDDもうつ病(精神障害)の一種ですが、症状は月経前の約2週間から月経開始頃までに限定されます。
しかし、抑うつ感やイライラなどの精神的症状が月経周期に関係なく現れる場合には、うつ病や双極性障害が疑われます。
いずれも自身の判断のみでは不十分なため、精神科や心療内科を受診しましょう。
更年期障害
更年期障害は、PMSと同様に女性ホルモンの影響を大きく受けて発症します。
ただし、PMSとは発症時期(年代)が異なります。
PMSは、思春期を終えて閉経を迎えるまでの性成熟期に多く見られる症状です。年代は10代後半から40代前半が該当します。
一方、更年期障害は閉経を迎える前後10年間を目安に現れる症状を指しています。
30代後半から40代の女性ではPMSと更年期障害の区別が付きにくいですが、月経周期に関係なく症状が現れる場合は更年期障害の可能性が高いでしょう。
- 気分の落ち込み
- イライラ
- 不安感
- 気分の浮き沈みが激しい
- 顔や身体のほてり、のぼせ
- 動悸
- めまい
- 身体や手足の冷え
- 肩こり
- 頭痛
- 腰痛
- 関節痛 など
更年期障害では漢方薬の他、ホルモン補充療法や抗うつ薬によって治療をおこないます。自身ではPMSと更年期障害の判別ができない場合には、婦人科や精神科を受診しましょう。
月経困難症
月経困難症は、PMSと同様に月経による影響を受けて発症します。双方の大きな違いは、症状が現れる時期です。
PMSは月経の約2週間前から始まり、月経が始まると徐々に治まります。一方、月経困難症は月経中に症状が強く現れます。
- ひどい月経痛
- 腰痛
- 頭痛
- 吐き気
- 気分の落ち込み
- イライラ
- 疲労感 など
PMSと月経困難症を併発することもありますが、処方される薬が異なる場合があるため、どちらも適切な治療を受けることが大切です。

まとめ
PMSは、月経周期に伴うホルモンバランスの変化や生活習慣によって発症します。
現代女性の大半が発症経験があるとされていますが、知識が不十分なために適切な対処方法を知らないまま過ごしている方も多いでしょう。
PMSの症状が辛い方は、本記事で紹介した対処方法をぜひ参考にしてみてください。
また、PMSではない病気の可能性も考えられるため、一度婦人科で相談することをおすすめします。
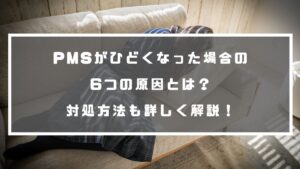
<参考>